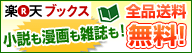茶の湯における立礼式(りゅうれいしき)茶法を考案したのは、
裏千家の11代家元・玄々斎(げんげんさい)精中だそうです。
近代茶道の先駆者と称される玄々斎は、
三河国奥殿藩4代藩主・松平乗友の子として1810(文化7)年に生まれ、
10歳で認得斎の婿養子として裏千家に入りました。
「講座 日本茶の湯全史 (第3巻 近代)」(茶の湯文化学会・編)の「近代茶家の復活」を参照すると、
玄々斎は立礼式茶法を明治元年には考案していたそうですが、
実用化されたのは1872(明治5)年に西本願寺・建仁寺・知恩院を会場として開催された
第一回京都博覧会だそうです。


椅子に座ってお茶をいただく立礼スタイルは、
京都万国博覧会に来場が見込まれた外国人にやさしい作法です。
この立礼スタイルの作法は、
ライフスタイルが変わり日常生活で正座する機会がほとんどなくなり、
また加齢による膝痛などにより正座が苦痛な人が増えてきている今、
現代人にとってもやさしい作法だと思います。
この様な時代変化に対応して
公共施設、文化施設などにある茶室には、
椅子に座ってお茶を頂くことができる
立礼席(りゅうれいせき)が設置されていることが少なくありません。
~ 大津市の「びわこ文化公園」にある「夕照庵(せきしょうあん)」の立礼席。
2013年11月15日利用。
~ 愛知県長久手市の「愛・地球博記念公園(モリコロパーク)」にある「香流亭(かなれてい)」の立礼席。
2014年3月18日利用。
~ 愛知県瀬戸市の「愛知県陶磁美術館」にある愛知県民茶室「陶翠庵(とうすいあん)」の立礼席。
2014年3月18日利用。
以上の3ヶ所のお茶室では開館当時から立礼席が設けられていましたが、
後から設置した茶室もあります。
~ 静岡県掛川市の「清水邸庭園」の広間に設置された立礼席。
2013年12月10日利用。
~ 愛知県豊明市文化会館の茶室「欅庵」の広間に設置された立礼席。
2014年1月4日利用。
~ 名古屋・八事の「八事山興正寺」の「竹翠亭」の広間に設置された立礼席。
2014年4月2日利用。